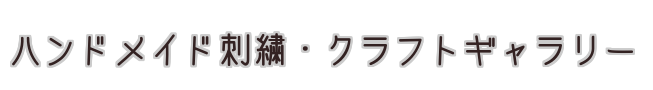表からは見えないけれど、仕上がりの美しさを左右する「裏側の処理」。刺繍を始めたばかりの頃は、つい表だけに気を取られてしまいますが、糸の始末や糸渡しの工夫ひとつで、作品の完成度が大きく変わるんです。
この記事では、刺繍の裏処理に関する基本と、わたしがふだん意識しているちょっとしたコツをご紹介します。
玉止めを使わない、すっきり仕上がる始末の方法
まず、裏処理で大事なのは「糸を玉止めしない」こと。手縫いではよく見かける処理ですが、刺繍では玉が裏にできると、厚みが出たり、引っかかりの原因になったりすることがあります。特にフレームに入れたり、身につける小物に仕立てるときは、裏のゴロつきが気になることも。
わたしがよく使っている方法は、刺し始めに数目分、裏側で糸を他の糸の間に通して固定するやり方です。終わりも同様に、数目の裏側に糸を通して処理します。慣れるととても簡単で、見た目にもすっきりしますよ。
また、図案の途中で糸を切り替えるときも、なるべく移動距離が短くなるように考えながら刺していくと、裏側がごちゃごちゃしにくくなります。
糸渡しの工夫で裏側のもたつきを防ぐ
刺繍中によくあるのが、隣同士でないモチーフを刺すときに、裏で糸を長く渡してしまうこと。これ、見た目は問題ないように感じますが、完成後に布が引きつれたり、糸が浮いてしまったりと、仕上がりに影響が出ることがあるんです。
糸を移動させたいときは、一度糸を切って新たに刺し始めたほうが、裏側がきれいに整います。少し面倒に感じるかもしれませんが、丁寧に処理しておくことで、後々の仕立てがスムーズです。
また、似た色同士の糸を使うときも、裏側で渡した糸が布の透け感によって表から見えてしまうこともあります。そんなときは、裏にフェルトや接着芯を当てるといいですよ。わたしは作品によって、裏打ちの素材を変えて使い分けています。
仕上がりに合わせて、裏の処理を選んでみる
作品をどう使うかによって、裏側の仕上げ方も少し変わってきます。
フレームに入れて飾る場合は、そこまで神経質にならなくても大丈夫。でも、ブローチやポーチのように触れる機会が多いアイテムでは、裏側の美しさも大事なポイントです。
わたしは、作品の用途に合わせて裏を「見せる仕上げ」にするか「隠す仕上げ」にするか決めています。見せるなら、糸の渡し方をより丁寧に。隠すなら、フェルトや布でカバーして肌当たりがやさしくなるように工夫します。
最後に、全体に軽くアイロンをかけて整えておくと、裏の糸も落ち着いて、きちんと感が増します。あて布を忘れずに、ふんわりと押さえるくらいでOK。裏まで気を配った作品は、自分の中でも「ちゃんと仕上がった」と感じられて、ちょっと誇らしい気持ちになりますよ。